『マリー・アントワネット』(原題: Marie Antoinette)は、2006年公開のアメリカ映画。ソフィア・コッポラが監督と脚本を手掛けた歴史ドラマで、フランス王妃マリー・アントワネットの波乱に満ちた生涯を描く。主演はキルスティン・ダンスト、共演にジェイソン・シュワルツマン、リップ・トーンらが名を連ねる。
物語は、オーストリアの皇女として生まれたマリーがフランス王太子ルイ16世と結婚し、絢爛豪華なヴェルサイユ宮殿での生活を送る中で、国民からの批判と孤立に直面する姿を描く。独特の現代的な音楽やファッションを取り入れることで、伝統的な歴史映画とは一線を画す斬新なスタイルが話題となった。
本作は第59回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールにノミネートされ、アカデミー賞では衣装デザイン賞を受賞するなど、高い評価を受けた一方で、歴史的描写を大胆にアレンジした内容について賛否が分かれた。
『マリー・アントワネット』のあらすじ紹介(ネタバレなし)
1770年、オーストリアの皇女マリー・アントワネットは、フランス王太子ルイ16世との政略結婚のため、わずか14歳でフランス宮廷に嫁ぐ。華やかなヴェルサイユ宮殿での生活に戸惑いながらも、宮廷の習慣や権力闘争に巻き込まれるマリー。孤独の中で贅沢な買い物や派手なパーティに熱中し、浪費癖や軽薄さを批判されるが、夫との関係や王妃としての責務にも悩み続ける。
やがて、ルイ16世が即位し、マリーはフランス王妃となるが、民衆の怒りが増大する中、王室への非難が集中する。革命の足音が迫る中で、マリーは家族とともにフランスを守るべく奔走するが、その運命は彼女の意志を超えて劇的な結末を迎えることとなる。
『マリー・アントワネット』の監督・主要キャスト
・ソフィア・コッポラ(35)監督
・キルスティン・ダンスト(24)マリー・アントワネット
・ジェイソン・シュワルツマン(26)ルイ16世
・ジュディ・デイヴィス(51)ノアイユ伯爵夫人
・スティーブ・クーガン(41)フロリモン・フランソワ・バルテルミ・モルパン伯爵
・アーシア・アルジェント(31)デュ・バリー夫人
・リップ・トーン(75)ルイ15世
・ダニー・ヒューストン(43)ジョゼフ2世
(年齢は映画公開当時のもの)
『マリー・アントワネット』の評価・レビュー
| ・みんなでワイワイ | 3.0 ★★★★☆ |
| ・大切な人と観たい | 3.0 ★★★☆☆ |
| ・ひとりでじっくり | 4.0 ★★★★☆ |
| ・10代のマリーアントワネット | 5.0 ★★★★★ |
| ・新しい歴史の視点 | 4.0 ★★★★☆ |
ポジティブ評価
ソフィア・コッポラ監督は『マリー・アントワネット』をポップに描く。
伝統的な歴史映画の枠を超え、現代的なアプローチで18世紀フランス王室を描いた点が大きな特徴。華やかで贅沢な宮廷生活をポップカルチャーの視点から再構築し、若い観客にも親しみやすい新しい歴史映画を作り上げた。特に、ザ・キュアーやボウ・ワウ・ワウといった現代的な音楽の挿入は、王妃マリー・アントワネットを「青春を生きる一人の女性」として描き出すユニークな効果をもたらしている。
キルスティン・ダンストの演技は、無邪気さと孤独感を持つマリー・アントワネットのキャラクターに説得力を与えた。彼女の自然体の演技は、観客に同情や共感を呼び起こし、単なる歴史的な人物像ではなく、一人の若い女性としてのマリーを印象的に描き出している。また、豪華な衣装や美術も必見。これによりアカデミー賞衣装デザイン賞を受賞した。
ネガティブまたは賛否が分かれる評価要素
歴史的な忠実性の欠如や斬新すぎる演出について批判的な意見も挙がった。物語の中心がマリー・アントワネットの個人的な感情や贅沢な生活に偏り、フランス革命の社会的・政治的背景や王妃が果たした歴史的役割についての描き方が不充分と感じる批評家も少なくない。
ソフィア・コッポラ監督独自の感性が強く反映されているが、その斬新さゆえに視聴者の好みや期待によって評価が分かれる作品となった。
こぼれ話
『マリー・アントワネット』は、フランス・ヴェルサイユ宮殿での撮影が許可され、史上初めて同宮殿のプチ・トリアノンや庭園などが映画のためにフルアクセスで使用された。この贅沢なロケーションが、18世紀の宮廷生活をリアルに描き出す大きな要因となった。
衣装デザインを手掛けたミレーナ・カノネロは、アカデミー賞を受賞した際に「伝統的なデザインに現代的な要素を取り入れる」というコンセプトを語っており、特に大胆な色使いやファッション雑誌のようなスタイリングが話題を呼んだ。興味深いことに、劇中に登場するマリーのシューズの中には、現代的なデザインのコンバースが映り込んでおり、監督ソフィア・コッポラの遊び心が垣間見える。
本作のラストシーンにマリーが断頭台へ向かう場面が描かれていないことも話題となった。この選択についてコッポラ監督は、「悲劇ではなく、彼女の人間性を描きたかった」と語っており、歴史映画としてよりも感覚的な作品としての位置付けが意図されている。




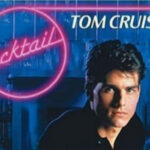






みんなのレビュー